現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
1.はじめに
シリーズ5、シリーズ6では、社債による資金調達について解説します。社債は、多額かつ長期の資金を調達する方法として、募集株式や借入と同様に、活用されるものです。社債の特徴をまとめると次のようになります。
≪社債の特徴≫
- 多額かつ長期
- 有価証券なので流動性あり、多数の者から調達が可能
- 利子によりコストが確定
- 償還がある
シリーズ5では、社債の特徴について、募集株式や借入と比較してその特徴点を把握してから、実際の募集手続きについて解説します。続けてシリーズ6では、少人数私募債の発行について解説します。会社法では、改正前商法で禁止されていた株式会社以外の会社による社債発行が認められるようになったことから、中小企業において少人数私募債の発行による資金調達も可能となりました。増資と借入以外の新たな手法として注目される資金調達手法でありますので、具体的に解説していきます。
2.社債と募集株式・借入金の比較
社債は、多額かつ長期の資金を調達する方法として多くの会社で活用されています。
ここで、社債と株式、社債と借入を比較してみると次のような共通点・相違点が考えられます。
|
株式
|
借入
|
|
|---|---|---|
| 共通点 |
|
|
| 相違点 |
|
|
上記のように、社債は有価証券の形態をとりますので、流動性があり、また多数の債権者が登場することが基本的に想定されています。このため、会社法において、社債管理者の設置義務(会社法702条)や社債権者集会の組織(会社法715条)などが規定され、社債権者の保護が図られています。また、多数の投資家の参加が予定されていることから、金融商品取引法において募集株式と同様に、50名以上への勧誘については有価証券の募集として、有価証券届出書等の情報開示義務があります(金融商品取引法5条他)。
近年では、銀行借入の場合も大型案件については、シンジケート・ローンによる協調融資が一般化しておりますので、必ずしも社債でなければ多額の資金が調達できないというわけではありません。ただ、金融機関が流動性を確保する目的で社債を好む場合も考えられますので、自社の利害関係者がどのような形態を好むのかを考えて、資金調達方法を考える必要があります。
また、社債の発行は株式のような株式の希薄化を起こさない一方で、負債比率は高めることになりますので、自社の目指す最適資本構成をもとにして、社債にすべきか株式にすべきかを決定することになります。
3.社債の発行手続の基本的な流れ
社債を発行する場合には、次の流れによって発行されます。
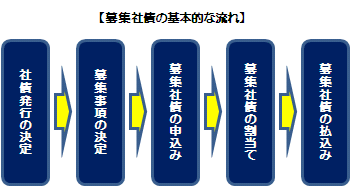
以下、この流れに沿って解説します。
(1)社債の発行の決定
社債発行は、業務執行行為の1つであるため、基本的には業務執行機関が決定します。このため、取締役会設置会社であれば、取締役会の専決事項のため、取締役会で社債の発行を決定することになります(会社法362条4項5号)。ただ、取締役会設置会社であっても、委員会設置会社の場合には、募集社債に関する事項の決定を取締役会の決議により、執行役に委任することが認められています(会社416条4項)ので、委任決議がなされている場合には、執行役が社債の発行を決定します。
なお、取締役会が設置されていない会社の場合には、取締役の多数決によって決定します(会社348条2項)。ただし、募集社債に関する事項の決定を業務執行権を有する取締役に委任している場合には(同3項)、その取締役が決定することになります。また、取締役会が設置されていなければ、株主総会において、会社の組織、運営、管理等のすべての事項を決議することができるので(会社295条1項)、定款に別段の定めがなくとも、募集社債に関する事項を決定することができます。
株式会社以外の会社(すなわち持分会社)においては、業務執行社員が決定することになります(会社法590条)。
(2)募集事項の決定
募集社債を発行する場合には、次の事項を決定します(会社法676条)。
- 募集社債の総額
- 各募集社債の金額
- 募集社債の利率
- 募集社債の償還の方法および期限
- 利息支払の方法および期限
- 社債券を発行するときは、その旨
- 社債券の記名式と無記名式の相互転換(698条)を制限する場合には、その旨
- 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに訴訟行為又は破産更生手続等に属する行為をすることができる(会社法706条1項2号)ときは、その旨
- 各募集社債の払込金額もしくはその最低金額またはこれらの算定方法
- 金銭の払込みの期日
- 打切発行としない場合には、その旨およびその一定の日
- ①~⑪に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
会社法においては、株券不発行の原則化と平仄を合わせる形で、社債券も不発行を原則としています(同条6号)。また、改正前商法では、打切発行にする旨を社債申込証に記載することを求めていましたが(つまり、打切発行が例外規定)、会社法では 社債は打切発行が原則となりました(同条11号)。
(3)募集社債の申込み
募集事項が決定したら、次に、募集事項を投資家に対して通知します(会社法677条1項)。これは、募集株式の場合と同様(会社法203条1項)に、投資家の投資判断のため、会社法においても一定の情報開示を求めているものです(会社法677条1項、会社法施行規則163条)。一方で、金融商品取引法規制において、目論見書を交付している場合等にも、募集株式と同様(会社法203条4項)に、会社法に基づく通知を省略することが認められています(会社法677条4項)。
この通知を受けて、募集社債の引受けの申込みをしようと考えた投資家は、①申込みをする者の氏名または名称および住所、②引き受けようとする募集社債の金額および金額ごとの数、③最低金額がある場合には(会社法676条9号)希望する払込金額の3つの事項を書面等により会社に交付します(会社法677条2項)。証券会社を利用している場合には、証券会社において手続きがなされると思いますので、証券会社が作成した申込書を利用する等が考えられます。
(4)募集社債の割当て・払込み
投資家から募集が集まったら、次は申込者の中から実際に誰にいくら引き受けてもらうか決定します。会社は、申込者が希望する金額通りに割り当てる必要は特にありません。募集株式の場合と同様(会社法204条1項)に、引き受けようとする金額を超えなければ問題ありません(会社法678条1項)。また、株式会社は、払込期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければなりません(会社法678条2項)。
社債の募集が完了したときは、払込期日(676条10号)に、割当てられた社債の金額を払い込むことになります。
4.社債の利払いと償還
社債は、一定日に決められた利息を支払い、また償還期限が到来すれば、社債を償還することになります。
社債の利払いは、一般的に社債に利札を付して、この利札と交換する形で支払われます。このとき、社債権者が自ら指定された支払場所に利札を持っていくことになりますので(これを持参債務といいます)、借入金のように債務者が自ら利息を支払うのと異なります。
社債の償還は、その償還日に償還することになります。ただし、実際には社債権者から社債を取得し、消滅させる「買入消却」の方法がよく用いられています(会社法690条1項参考)。社債の買入消却は、マーケット価格が下落しているときは、償還よりも有利な方法になります。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

